
|

|
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 四国遍路ひとり歩き同行二人 (解説編) |
宮崎 建樹 (みやざき たてき) | 四国遍路を始めるに当たって必要な知識を与えてくれる良書。
遍路の仕方、巡拝計画の立て方、「へんろ用品」の紹介、その他装備品、霊場での作法、遍路の心得、
その他「四国遍路」に必要な多くの情報が記載されている。 また、すべての札所(88カ所)のほか、別格20霊場や番外霊場も含む霊場についての情報が 巻末にまとめられている。 |

|
1935年生まれ。40代の頃、大病で入院したのをきっかけに、歩き遍路を始めたが、
遍路道が分かりづらいのに気づき、
独力でへんろみち保存協力会
を立ち上げ、へんろみちの要所要所に案内板を立てる活動のほか、遍路初心者のための案内書(解説編、地図編)の出版を始める。 「平成の真念」とでも言うべき方で、現在「歩き遍路」をする人で、宮崎さんの(有形・無形の)お世話にならない人はいないだろう。 2010年11月逝去。 |
|
| へんろみち保存協力会 2004年4月1日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 四国遍路ひとり歩き同行二人 (地図編) |
宮崎 建樹 (みやざき たてき) | 「歩き遍路」には必要不可欠、これ以上のものはないと思われる地図。
別格20霊場や番外霊場を含む各札所の位置と、民宿、ビジネスホテル、宿坊などの宿の位置、さらには、
途中にある食堂やスーパー、コンビニ及び郵便局の位置なども網羅されている。 巻末には、四国霊場と宿泊施設一覧表があり、それぞれの地点から前後の札所までの距離、電話番号、所在地 なども記載されていて、宿泊予約などにも不可欠な情報満載である。 |

|
上に同じ。 宮崎さんは、『地図編』の改訂に継続して取り組んでこられたが、2010年11月に、松山市郊外の山中にある俵飛山福見寺へ の参詣道の調査に入ったところで、山道から転落して亡くなられた。 朝日新聞の夕刊(2011/1/29)に掲載された『惜別』の記事は、 こちらで見られます。 1935年生まれ。40代の頃、大病で入院したのをきっかけに、 歩き遍路を始めたが、遍路道が分かりづらいのに気づき、独力でへんろみち保存協力会を立ち上げ、 へんろみちの要所要所に案内板を立てる活動を行うとともに、遍路初心者のための案内書(解説編、地図編)の出版を始める。 「平成の真念」とでも言うべき方であって、現在「歩き遍路」をする人で、この方の(有形・無形の)お世話にならない人は いないだろう。 |
|
| へんろみち保存協力会 2006年4月25日発行 |
| 書 名 | 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
|
ドライブお遍路 四国八十八ヵ所クルマ巡礼 |
KG情報 2007年9月20日発行 |
「歩き」ではなく、車を使って八十八ヵ所を巡拝する場合、
大変便利な地図帳。 たまたま、インターネットで見つけたので購入しておいたが、2008年春と2009年春の二回に分けて、 妻と一緒に「車遍路」をした際に、大変役に立った。 札所間の地図は、『地図編』ほど詳細ではないが、 車で回る場合には、これで充分だろう。 それぞれの札所の写真や、簡単な解説があり、特に、本堂や大師堂に対する駐車場の位置関係が 図示されているのは、車で巡拝する際に大変ありがたい情報である。 詳細はこちら |

|
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 四国遍のはじめ方 | 串間 洋 (くしま ひろし) |
1996年から6回に分けて行った歩き遍路の経験をもとに、全くの素人がお遍路を始めるに当たって心がけるべきこと、
準備すべきものなど、かみ砕くように解説してくれている「歩き遍路」の入門書。 必ずしもお大師信仰に基づかない「趣味(pastime)」としての「お遍路」のあり方についての貴重な情報が満載。 著者による本書の紹介はこちら。 著者は、この歩き遍路経験をもとに、「掬水へんろ館」という ホームページを立ち上げている。 このサイトには、四国遍路に関心のあるすべての人がアクセスしていると言っても過言ではない。 |

|
1960年熊本県生まれ。1浪1留年を経て、1975年、東北大学工学部応用物理学科卒業と
同時に大手電機メーカー入社。 以来、システムエンジニアとして機械翻訳システムの開発、システム技術支援などに従事。 現在、環境分野の事業企画を担当。横浜市在住、1996年より歩き遍路を始め、2002年1月までに2巡。 歩き遍路をテーマとするホームページ「掬水へんろ館」館主。 著者ホームページ:http://www.kushima.com/henro/ |
|
| 明日香出版社 2003年10月31日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| これがほんまの四国遍路 | 大野 正義 (おおの まさよし) | 「歩き遍路」を9回満願した著者が、従来の「遍路の常識」に疑問を持ち、
多くの資料を読破した結果としての卓説を展開している。
特に、「遍路の父」と言われる真念がその著書『四国邊路道指南』で札所を
現在の八十八ヵ所に限定してしまったことに対する批評は辛辣である。 「お遍路のタイプ別分類」「遍路歩きの戦略と装備」「道と宿についての考察」など、初心者のみならず 歩き遍路経験者にも「読めば眼から鱗」とも言うべき内容が含まれている。 「別コースの遍路道」は、これから歩こうとする人にとって、一読の価値あり。 著者による非常に充実した ホームページには、 本書の元になった内容が詳細に記されている。 |

|
1936年大阪府生まれ。立命館大学卒業後、門真市役所に勤務。企画室長、自治推進部長、
市民部長、市史編纂室長などを歴任。市史編纂時代より精力的に郷土史研究に取り組み、学術的価値の高い
史料を多数発掘。 1997年に定年退職後は四国遍路9回のほか、西国33ヵ所巡礼、熊野古道、奥の細道、長崎26聖人などの 巡礼を重ね、その経験から定説にとらわれない論理的で斬新な巡礼論考をウェブ上に発表し続けている。 |
|
| 講談社現代新書 2007年2月20日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| お遍路 | 高群 逸枝 (たかむれ いつえ) | 著者は、24歳の時に行った「四国遍路」を再度実行しようとして果たせなかったが、 後に回想しつつまとめた書。前著『娘巡礼記』より洗練された書きぶりに なっており、交通機関や道路も未発達であった当時(大正時代)の四国遍路がどのようなものであったかを知るのに 貴重な資料である。旅の途上で著者自身が作った和歌などもまとめて記されている。 |

|
明治27年(1894)熊本県に生まれる。県立熊本師範学校女子部を退学後、熊本女学校四年を修了。
大正7年四国遍路を行い、九州日日新聞に巡礼記を発表する。(死後『娘巡礼記』として刊行される。)
大正9年上京し、詩集『日月の上に』を世に出す。昭和5~6年雑誌『婦人戦線』を主宰し、評論でも活躍。
のち女性史研究に専念する。 著書に『母系制の研究』『招婿婚の研究』『大日本女性人名辞書』『女性の歴史』『日本婚姻史』 『火の国の女の日記』などがあり、主なものは『高群逸枝全集』に収められている。昭和39年病没。 |
|
| 中公文庫 1987年12月--日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 平成娘巡礼記 | 月岡 祐紀子 (つきおか ゆきこ) | 日本にはほとんどいなくなった瞽女(ごぜ)三味線
の継承者として活躍中の女性が、写真家二木三和さんと二人で2度目の歩き遍路を行ったときの記録。
第1回目(1999年秋)には一人で、各札所の本堂で瞽女唄を奉納しながら回ったが、このとき辰濃和男さんに
出会っている。(この間の状況は、『四国遍路』に出ている) 月岡祐紀子さんのホームページはこちら。 |

|
東京、目黒生まれ。武蔵野女子大学卒業。NHK邦楽技能者育成会卒。平成13年、ドキュメンタリー 「娘三味線へんろ旅」で放送文化基金の出演者賞を受賞。舞台では民謡唄、三味線にとどまらず、洋楽器との 合奏も多い。ごぜ三味線の数少ない継承者の一人として、また、歩きへんろの若き語り部として各方面から 注目を集めつつある。 | |
| 文春新書 2002年8月20日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 道 楽 | 藤原 宣昭 (ふじわら のぶあき) | 本サイト管理人の友人(藤原宣昭氏)が、50歳を過ぎて再開した山歩き (主として「東海自然歩道の往復踏破」など)の途中で感じたこと考えたことなどをエッセイ風に書き留めた ものを纏めた。 |

|
1942年兵庫県生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士課程修了。工学博士。
株式会社TES副社長、株式会社アクアテック副社長
などを歴任。 2006年6月逝去。 |
|
| 自費出版 (非売品) 1999年10月31日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 気紛れ歳時記 | 藤原 宣昭 (ふじわら のぶあき) | 本サイト管理人の友人(藤原宣昭氏)が、四季折々の季節の便りを友人宛に
E-mailで送ったものを纏(まと)めて、ご長男(岳典氏)が出版したもの。 藤原宣昭氏は、2001年の連休に6日間かけて阿波の札所23ヶ所を打ったが、その年の12月に尿管に癌が見つかり、 2002年1月に手術を受けたあと、闘病生活に入った。いつかは土佐入りすると言い続けていたが、 薬石功無く2006年6月に逝去された。 本書の内容は、 『気まぐれ歳時記』 のサイトで読むことができる。 |

|
1942年兵庫県生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士課程修了。
株式会社TES副社長、
株式会社アクアテック副社長などを歴任。 ほかに、こよなく愛した「歩き旅」のことを綴った『道楽』(自費出版)がある。 2006年6月逝去。 |
|
| 自費出版 (非売品) 2006年7月24日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 四国八十八ヶ所の旅 | 写真 : 大森 忠 (おおもり ただし) 文 : 壇上 完爾 (だんじょう かんじ) |
各札所の特徴を写真入ページで紹介。 後半には、遍路の心得や、各地の観光名所を紹介している。 車遍路を対象としている。 |

|
||
| 淡交社 1999年7月14日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 巡 る 楽 園 | 三好 和義 (みよし かずよし) | 第1番札所から始まり八十八番・大窪寺を経て高野山に到る霊場で、
3年間の歳月と4万キロに及ぶ撮影行で撮影された、これぞプロの写真家と思わせるアングルの写真300枚余りが
掲載されている。 巻末には、徳島県生まれで高野山真言宗・般若院住職の宮崎信也氏との対談や各札所の紹介などもある。 郵便局で発行している、ふるさと切手 「四国八十八ヶ所の文化遺産」は、三好和義氏の撮影になる原画を使用している。 著者のホームページはこちら。 |

|
1958年徳島市生まれ。13歳の時沖縄を訪ねて以来、タヒチ、
モルディブ、南極からチベットまで世界各地で「楽園」をテーマに撮影を続けている。
また近年は四季に富んだ日本の中にも「楽園」を見出し、10年をかけて屋久島を』撮り下ろした。 第4回飯田市藤本四八写真文化賞を受賞。主な写真集に『ぼくのふるさと 阿波吉野川』『楽園大百科』 『世界遺産 屋久島』『ニライカナイ-神の住む楽園・沖縄』(以上小学館)ほか多数。 |
|
| 小学館 2004年1月10日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
|
花へんろ -風の昭和日記- |
早坂 暁 (はやさか あきら) |
遍路道に面する商家で生まれ育ち、幼少の頃からお遍路さんに接してきた経験をふまえ、
松山近郊にある自分の生家を舞台にして、地方から眺めた「昭和という時代」を、
「私小説」に対する「私ドラマ」として表現している。 後に、このドラマを小説にしたもの 『花へんろ 夢の巻・風の巻・海の巻』が刊行されている。 |

|
1929年、愛媛県・北条市(現松山市)生まれ。
松山中学を経て、海軍兵学校在学中に終戦。旧制松山高等学校卒業後、日本大学藝術学部演劇学科卒。
業界新聞編集長を経て『ガラスの部屋』(1961年、日本テレビ)で脚本家デビュー。
以後、1000本以上の映画やドラマの脚本、小説を手がけ、人間をテーマにした独自の作風を築く。 新田次郎文学賞、講談社エッセイ賞、向田邦子賞、放送文化基金賞、芸術選奨文部大臣賞、 紫綬褒章、芸術祭優秀賞、放送文化賞ほか多数の受賞歴がある。 |
|
| 大和書房 1986年9月30日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 青春デンデケデケデケ | 芦原 すなお (あしはら すなお) | 1960年代、香川県観音寺市の
県立高校の生徒たちが、
エレキギターのバンドを作って活躍する青春物語。 「讃岐弁」を縦横に駆使したユーモラスな語り口の中に、当時の時代背景が浮かび上がる。 本サイト管理人の妻がこの高校を卒業したこともあり、大変面白く読んだ。 |
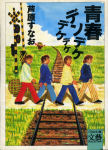
|
1949年、香川県・観音寺生まれ。
早稲田大学大学院博士課程中退。1990年、『青春デンデケデケデケ』で第27回文藝賞、
翌91年、第105回直木賞を受賞する。
他の著書に『スサノオ自伝』がある。
|
|
| 河出文庫 1992年10月2日発行 |
| 書 名 |
著 者 略 歴 出 版 社 |
概 要 |
|---|---|---|
|
花へんろ 夢の巻・風の巻・海の巻 |
早坂 暁 (はやさか あきら) |
「私ドラマ」として書かれた『花へんろ -風の昭和日記-』
を、小説に書き直した作品。「しんぶん赤旗 日曜版」に掲載されたものを纏めて出版された。 「夢の巻」、「風の巻」、「海の巻」の三部から構成されており、大正時代の終わり(関東大震災の頃)、 著者の母が叔母の嫁ぎ先の息子(従兄)と結婚するところから始まる。日本が「支那事変(日中戦争)」を経て、 太平洋戦争に突入して行く時代背景を、愛媛の片田舎における人々の暮らしの中から見つめた情景を描き出している。 太平洋戦争の終戦直後まで、著者の母を主人公にした形で物語が展開して行くが、全編にわたって、 「反戦」という主張が貫かれている。 |

|
1929年、愛媛県松山市生まれ。
作家。本名、富田祥資。日本大学芸術学部演劇学科卒業後、業界紙編集長、出版事業に従事しながら
テレビシナリオを書き始める。以後、小説、映画シナリオ、戯曲、舞台演出、ドキュメンタリー製作を手がける。 代表作に、「夢千代日記」「花へんろ」「天下御免」「天国の駅」「ダウンタウンヒーローズ」 「華日記」「公園通りの猫たち」などがある。 新田次郎文学賞、講談社エッセイ賞、放送文化基金賞、芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、芸術祭大賞、 モンテカルロ国際テレビ祭脚本賞、放送文化賞受賞多数。 |
|
| 勉誠出版 2008年6月30日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 著 者・訳 者 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
|
三 教 指 帰 (さんごうしいき) |
空海 (くうかい) (弘法大師) 加藤精神 (かとう せいしん) 訳註 |
儒教・仏教・道教の三教の基本的な立場を対話形式で示し、 最勝の教としての仏教の意義を明らかにした、空海24歳の処女作。 |

|
岩波文庫 1935年2月25日発行 |
| 書 名 | 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
|
修 證 義 (しゅしょうぎ) |
大本山 永平寺 |
以前、座禅の会に参加した際にいただいたもの。 開經偈、懺悔文、三歸戒文、般若心経、修證義、普門品偈、舎利禮文、四弘誓願文、 食事訓、回向などが含まれる。 この中で、「修證義」は、道元の『正法眼蔵』から抜粋したもので、 1890(明治23)年に刊行された。 |

|
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 般 若 心 経 | 金岡 秀友 (かなおか しゅうゆう) | 簡潔に省略化された「般若心経」の省略された部分まで広げて解釈すべく
詳しく解説されている。 現在最も広く流布されている三蔵法師玄奘訳に基づいているが、各国で翻訳されたものや注釈などに ついても言及し、空海による『般若心経秘鍵』の独自性にも触れている。 途中で引用されている江戸時代の「絵心経」 (えしんぎょう)は興味深い。 |
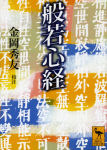
|
1927年埼玉県生まれ。東京大学文学部インド哲学科卒業。現在、東洋大学名誉教授 真言宗妙薬寺住職。主著に『密教成立論』『密教の起源』『仏教の国家論』、訳書にシチェルパトスコイ『大乗仏教概論』 『小乗仏教概論」。講談社学術文庫に『密教の哲学』がある。 | |
| 講談社学術文庫 2001年4月10日発行 |
| 書 名 | 著 者 略 歴 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
|
賢 者 の 説 黙 -理趣経の智慧- |
瀧 城太郎 (たき じょうたろう) | 真言宗が非常に大切にしている「理趣経」の解説書である。
不空三蔵の『理趣釈』を基にしつつ、著者自身の解釈を述べるという体裁をとっているが、
何度読んでも完全に理解するところまでには到らない。 著者が住職を務める田福寺の檀家総代である なかにし君 (本サイト管理者の友人)から聞いたところによると、「最近の僧侶は何も知らない」ので、 全国の僧侶を啓蒙する目的で書かれたものらしいということで、我々素人が理解するのは もともと無理な話なのかもしれない。 |
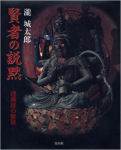
|
本名、瀧 智真。和歌山市出身。東京大学文学部インド哲学科卒業。 平成14年、密教小説『結子(ゆうこ)』を発表し、執筆活動を始める。 現在、田福寺(和歌山市)住職。 |
|
| 青山社 2003年9月6日発行 |
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| る る ぶ | JTBパブリッシング 2005年3月1日発行 |
「るるぶ 情報版」の一冊。『同行二人 巡礼の道』と題し、
準備、作法、計画などの一般的な情報に加えて、各札所の由来、特徴・見所など詳しい。 周辺での食べ物、お土産などのコラムもあって、事前に読んでおけば、肝心なところを見落とさずにすむ。 |

|
| 書 名 | 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| NHK 趣味悠々 | 日本放送出版協会 2006年9月1日発行 |
2006年9月から11月にかけてNHK教育TVで放映された
「趣味悠々 四国八十八ヵ所 初めてのお遍路」のテキスト。 「計画の立て方」「参拝作法」から道中の案内、遍路宿など「あるきへんろ」を始めるのに必要不可欠な 「知識」を多くの写真を添えて紹介している。 |
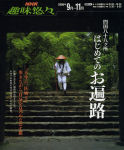
|
| ページトップに戻る |
| 書 名 | 監 修 者 ・ 出 版 社 | 概 要 |
|---|---|---|
| 日本大歳時記 | 監修者 水原 秋桜子 (みずはら しゅうおうし) 加藤 楸邨 (かとう しゅうそん) 山本 健吉 (やまもと けんきち) |
花鳥風月のカラー写真を多く配し、 例句も多数入れた本格的な歳時記。 「新年」「春」「夏」「秋」「冬」の5分冊からなる。 |

|
講談社 1981年11月25日発行 |
| ページトップに戻る |