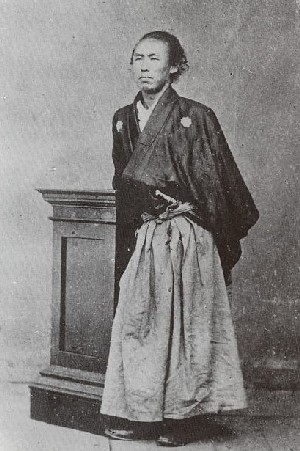| 前(第4回)に戻る | 紀州弁 Top に戻る | 次(第6回)へ |
| 地震には自信がある? | 四つガナの区別と混同 | ||
|
前回、紀州人は「d」と「z」の発音の区別ができないと書きましたが、 実は、紀州人に限らず現代の日本人は必ずしも完璧に [d] と [z] の区別が できるとは言えないのです。 読者の皆さんは「ジ」と「ヂ」、「ズ」と「ヅ」をそれぞれ区別して 発音していますか? これは、現在ほとんどの日本人が区別できなくなっている 音なのです。
しかし国語学者によると、江戸時代のはじめ頃から、一部の地域を除いて、 これらの発音の区別がなくなってきたようで、 この現象は『四つガナの混同』と呼ばれています。 この結果として、現在の日本語では「自信」、「地震」、「自身」、「磁針」などは アクセントは別にして、発音上の区別がありません。 特に「地」の字は、本来は濁音として読むときは「ヂ」と読んでいたはずなのに、 今では辞書でさえ「ジ」と読ませています。 また、今では「ラジオ」と書いている Radio のことを、昔は「ラヂオ」と書いていたのを 覚えている方もいるでしょう。 「縮む」や「続く」は今でも辞書では「チヂム」、「ツヅク」とカナをふっていますし、 「缶詰」も当然「カンヅメ」ですが、話し言葉では「チジム」、「ツズク」、「カンズメ」 などと言っても、音としては区別できませんから、間違いではありません。 ところが、これらの言葉をワープロで入力して漢字に変換しようとすると、 大抵の日本人は [d] で入力すべきか [z] で入力すべきかで迷うことになります。 これは、「ジ」、「ヂ」、と「ズ」、「ヅ」だけの話なのですが、紀州人は 「ザ行」と「ダ行」のすべて([ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ] と [ダ、ヂ、ヅ、デ、ド])について、 いつも同じような困難を覚えているのです。 筆者の勤務先にいる富士田さんは那賀郡粉河町で生まれ育った方ですが、 ワープロで書類を作っているとき、 [d] と [z] のどちらが正しいか分からないまま 入力していて、 [d] でうまく変換できなければ [z] で入力し直すということをやっています。 ですから、3回くらい続けて正しく変換されると、「今日は調子がいいな!」と思ったり、 「ここ2、3回は [z] でうまくいっているから、次の漢字では [d] を使ってみるか」 と考えたりしているそうです。 要するに、「ザ行」と「ダ行」の区別に関して、全く自信がないということです。 この項のはじめに、日本では一部の地域を除いて「ジ」と「ヂ」、「ズ」と「ヅ」 の区別をしなくなっていると書きましたが、この区別をしている「一部の地域」というのは 実は高知県のことです。 大阪府池田市にある、国立の研究所で所長をしておられた巖元さんは、 高知県の出身ですが、筆者は10年くらい前、ある会議でいつも巖元さんと ご一緒する機会がありました。 紀州弁のことを調べはじめた最近になって、筆者は、巖元さんが、「縮める」は [chijimeru] でなく [tidimeru] 、「続く」は [tsuzuku] ではなく [tuduku] と 五十音図どおりの“正しい”発音で話していたのを思い出します。 本来の日本語という意味では、高知県の人々がしゃべっている言葉は正しい日本語なのですが、 『四つガナの混同』が日本全土に拡がってしまった 今となっては、却って、これらを区別している高知県の人たちの『四つガナ弁』が “訛って”いるように聞き取られてしまうのです。 逆に「ジ」、「ヂ」、「ズ」、「ヅ」の『四つガナ』を全く区別しないのが、東北地方の いわゆる「ズーズー弁」です。 たとえば、この地域の人たちは「家事」と 「数」をほとんど区別せずに話しているように聞こえます。 国語学者(方言学者)の中には、紀州弁のような「ザ行」と「ダ行」の混同は、 『四つガナの混同』の延長線上にあると捉えて、 将来の日本語は「ザ行」と「ダ行」の区別がなくなる方向に 行くのではないかと考える人もいるようです。 だからといって、『紀州弁は日本語の最先端を行っている!』というのは、 少々言い過ぎろうだとは思いますが・・・。 |
|||
| 前(第4回)に戻る | 紀州弁 Top に戻る | 次(第6回)へ |